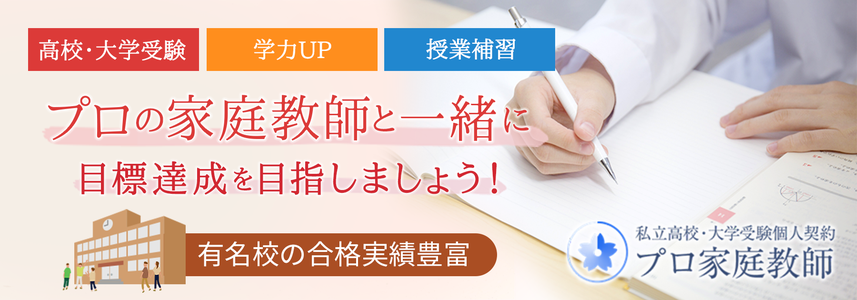浪人生の方へ


予備校に通えば安心???

浪人を決断した際、まず思い浮かぶのは予備校に通うことだと思います。
大手の予備校は、有名大学への多数の合格実績があり、志望校に落ちて傷ついた心を癒してくれる十分な信頼感があります。「寄らば大樹の陰」という考え方は、決して間違った選択ではありません。
しかし、夏を過ぎた頃になると、思うように成績が伸びないという生徒が多く、相談に来るご家庭のほとんどは、全日制の有名予備校(S台・K塾)に通っている生徒さんたちです。この現実もまた、間違いのない事実です。
わたくしが予備校をおすすめしない理由
予備校は、「一定の学力がある生徒さん」、つまり上位2割に入るような生徒や、選抜試験で上位クラスに入学した生徒にとっては、志望校合格のための最良の教育機関となり得ます。こうした生徒たちは、予備校のカリキュラムや指導を最大限に活用し、さらに成績を伸ばすための場として、非常に有効に機能します。
しかし、それ以外の生徒、特に成績が中位以下の生徒にとっては、予備校は必ずしも最適な選択肢ではありません。予備校では、成績上位層が重点的に指導され、下位層の生徒はその影響を受けにくく、個別のサポートが十分に得られないことが多いです。その結果、予備校に通っているにも関わらず、志望校に合格できなかったり、その下位の大学にすら合格できないというケースがよく見受けられます。結局、多くの生徒は、ただの「お客さま」扱いになり、結果的に予備校のシステムにうまく適応できず、望む結果を得ることができないことが少なくないのです。


1
高等学校の授業同様、志望校の出題傾向に直結しなかったり、自分のレベルに合わない講義や模試等、時間とお金の無駄が多い
2
生徒さんの現在の学力を判断し、苦手分野を克服させること、並びに、志望校に特化した対策(過去問つぶし等)が全くないか、あったとしても多数の生徒を抱えているため手薄である
3
予備校のカリキュラム上、7月までに全科目1周し、それ以降は復習・演習となるため、個人の弱点や苦手科目を補強する機会に乏しい
4
講義形式なので、講師の名講義(「今でしょ!」など)を聴いているだけにもかかわらず、自分で勉強ができるようになった気になり、成績は上がらないままである
5
無選抜クラス、あるいは、選抜クラスでも下位クラスに行くほど、講師の質が下がるのが一般的である
6
予備校テキスト主体の勉強になるため、入試直前に心のよりどころとなる「やり切った」参考書や問題集を持てない
7
クラス担任やチューターは相談に乗ってはくれるものの、講義の現場を知らない予備校スタッフの質に疑問があり、学生アルバイトは個人の経験だけでものを言うので信頼性に乏しい
8
孤独な戦いとなる受験勉強に不可欠なメンタル面でのフォローが乏しい
合格への近道は家庭教師


経済的にかなりの負担がかかることは確かですが、それでも私は断言します。
「家庭教師をメインに、予備校をサポート的に利用する受験勉強こそ、志望校合格への最短ルートである」
と。
具体的な方法としては、まず家庭教師による学習カリキュラムに基づいて、計画的に学習を進めることが非常に重要です。家庭教師は個別に指導を行い、弱点を徹底的に克服しながら、志望校合格に向けて必要な知識とテクニックを伝授してくれます。予備校は、集団の授業で効率よく進めるための場所として、従として活用する形が理想的です。
さらに、志望校に直結した模試を受けることもポイントです。模試を通じて、実際の試験形式に慣れることができ、現状の実力を確認し、改善すべき点を把握することができます。予備校の模試や大規模な試験に関しては、進度や内容が必ずしも志望校の試験と一致するわけではないため、目標に合った模試を選ぶことが大切です。
最後に、モチベーションを維持し、さらに高めるためには季節講習会を受講するのも非常に効果的です。夏期講習や冬期講習など、特定の時期に集中して学ぶことで、弱点を集中的に克服できると同時に、受験への集中力を高めることができます。これらを組み合わせることで、受験勉強はより効率的で効果的に進められ、志望校合格に向けて強固な基盤が築けるのです。